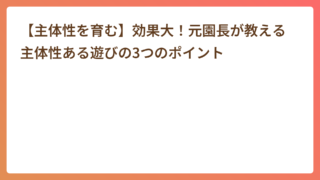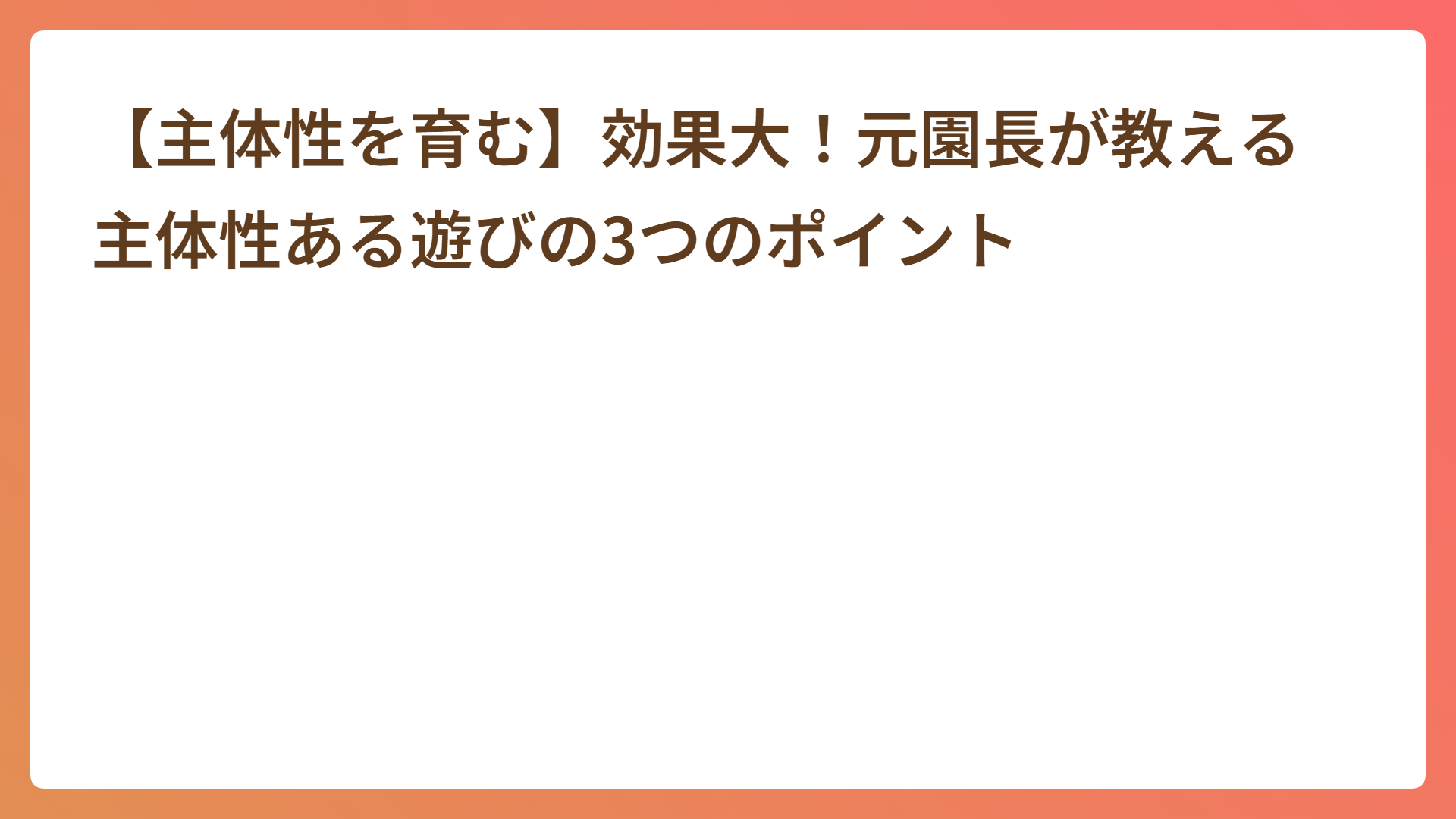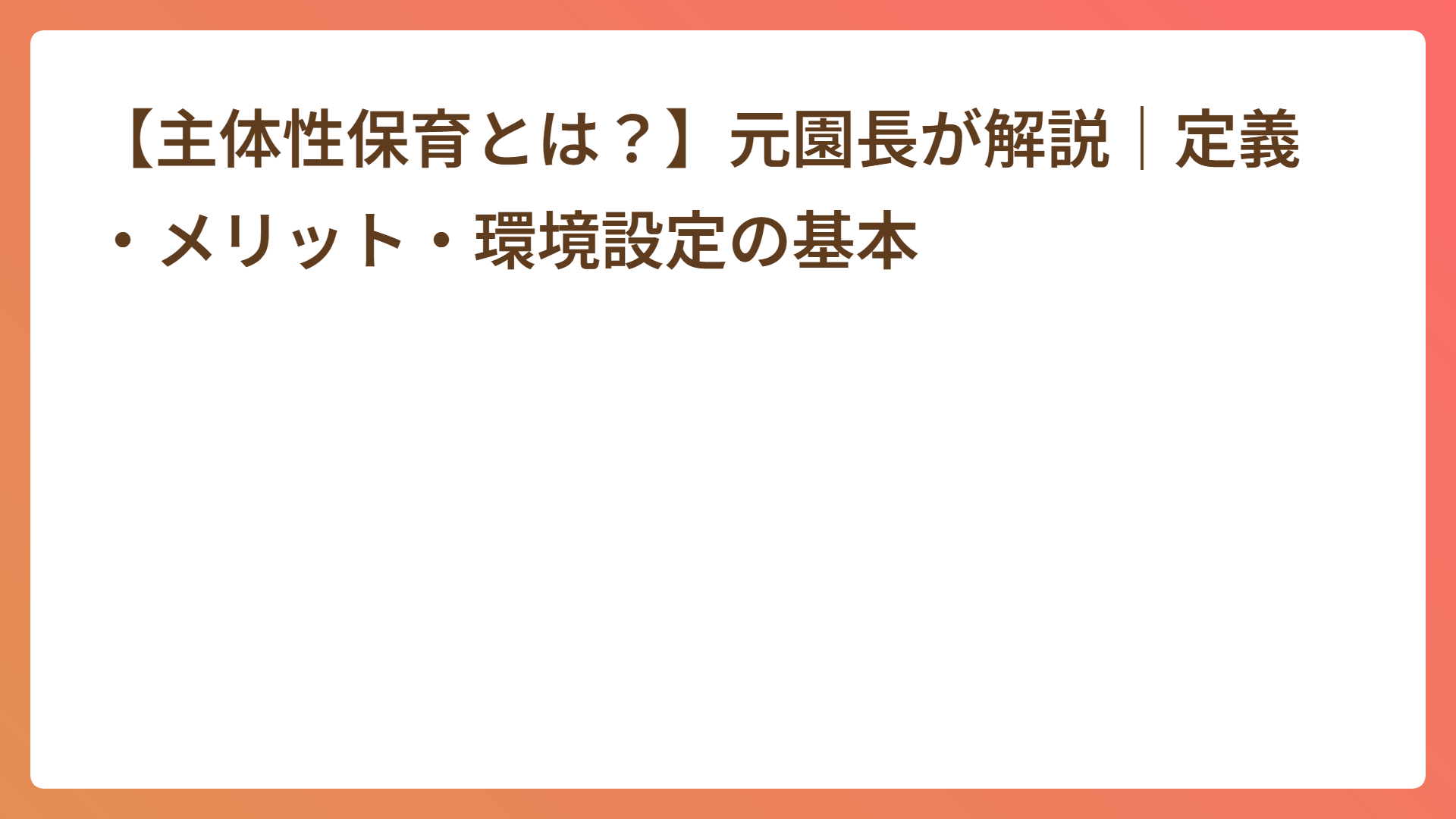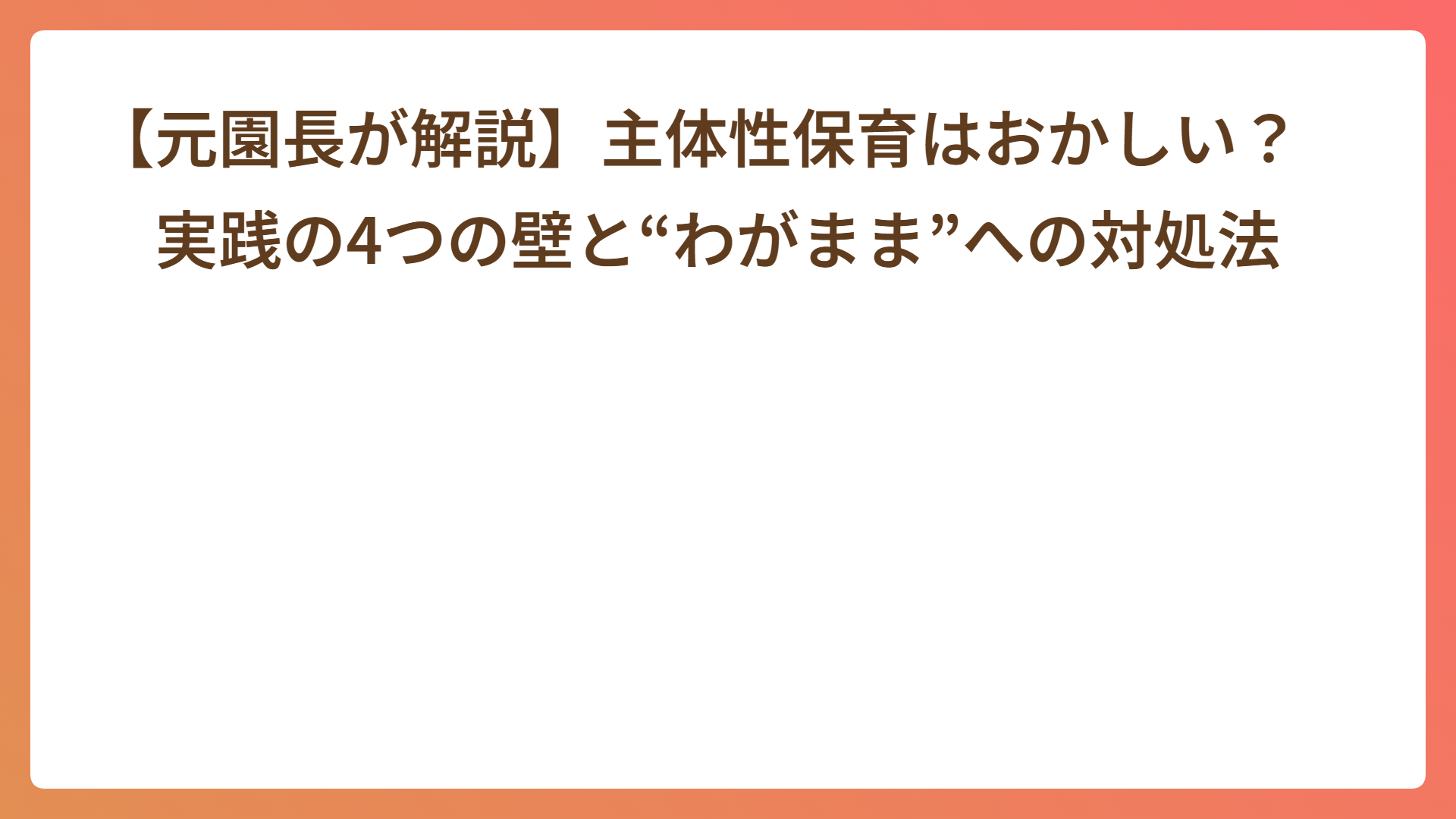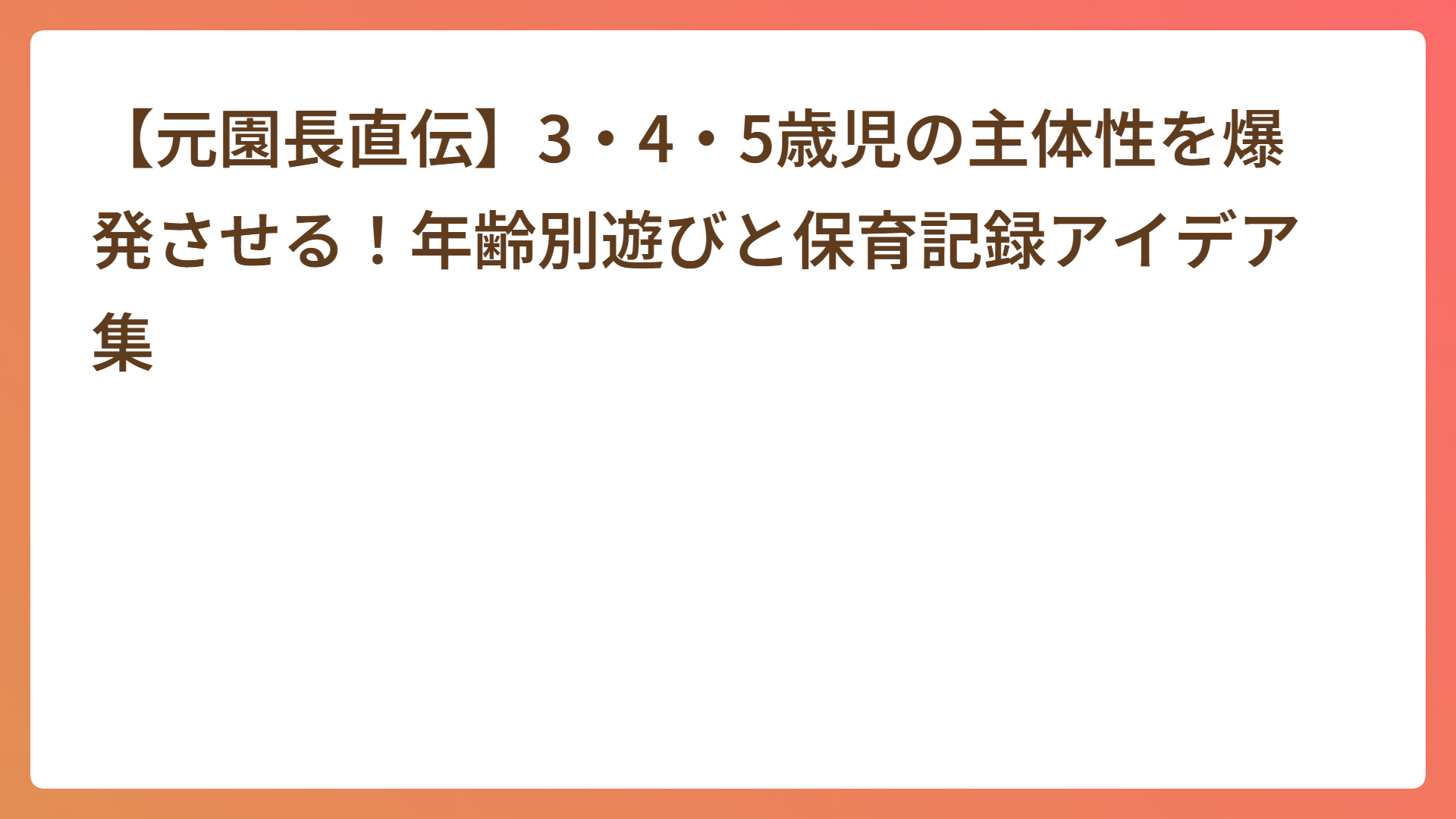元012歳園の園長が教える!保育記録に使える012歳児の主体性を育むアイデア集
このブログでは、保育士歴10年(012歳園の園長経験4年)の私が、明日からの保育が少しでも楽になるような情報や考え方を発信しています。

低年齢の子どもたちに主体性保育って、どうやって取り入れたらいいんだろう……

ご安心ください!
この記事では0・1・2歳児専門保育園の園長として子どもたちの「主体性」を育む保育に情熱を注いできた私が、その具体的な方法を分かりやすくお伝えします
子どもたちの「やってみたい!」という輝く瞳と、その小さな一歩を大切に育む関わりこそが主体性保育。
この記事を読むことで、元園長の経験に基づいた、012歳の低年齢児向けの具体的な主体性保育のアイデアが分かり、日々の保育に自信を持って取り組めるようになります。
皆さんの保育がよりよいものになって、子どもたち一人ひとりの可能性を最大限に引き出すお手伝いをしていきます。
主体性保育とは? – 子どもの「やってみたい!」を原動力に

主体性保育とは、一言でいえば「子どもが自ら興味・関心のある対象を見つけ、積極的に関わろうとする力を育む保育」のことです。
大人が指示してやらせるのではなく、子ども自身の「やってみたい!」「知りたい!」という内側から湧き出るエネルギーを原動力として、遊びや生活を通して学びを深めていくことを大切にします。
- 自己肯定感の向上
- 思考力・判断力・表現力
- 集中力・探求心
- 社会性・協調性
主体性保育の基本やメリットについてさらに詳しく知りたい方は、ぜひこちらの記事もご覧ください。
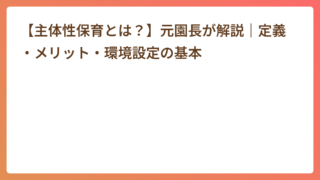
【0歳児】安心して世界と関わる第一歩!主体性を育むアイデア

0歳児の主体性は、「快・不快」の感覚や、心地よいものへの興味・関心から芽生えます。
保育士の役割は、まず何よりも安心できる愛着関係を築き、子どもが発するサインを敏感にキャッチして応答することです。
0歳児室内遊びのアイデア:五感を刺激する「ふれあい素材コーナー」
- ねらい
様々な素材に触れることで感覚機能を豊かにし、自ら手を伸ばし探索する意欲を育む。 - 準備するもの
安全で多様な感触の素材(オーガンジーのような薄い布、毛糸玉、スポンジ、様々な形の木のブロック、音の出るガラガラ、握りやすい布製ボールなど)や子どもが寝転んだり座ったりした状態で手を伸ばしやすいマット、浅めのカゴ - 保育士の関わり方:
- 子どもがリラックスできる空間に、素材を数種類ずつ、ゆったりと配置します。
- 子どもが自ら興味を示し、手を伸ばしたり、口に持っていったりするのを待ちます。急かしたり、無理強いしたりはしません。
- 子どもが素材に触れたら、「ふわふわだね」「つるつるしてるね」「カシャカシャ音がするね」など、その感触や音を言葉にして伝えます。喃語や表情に応答し、共感を示します。
- 素材を口に入れて確かめるのも大切な探索行動ですが、誤飲や衛生面には十分注意し、常に安全を確認しながら見守ります。
- 「〇〇ちゃん、自分で選んで触っているね。面白いね」と、その主体的な行動を認め、子どものペースを尊重します。
0歳児戸外遊びのアイデア:自然を感じる「やさしい外気浴」
- ねらい
外の空気、光、音、風などを五感で感じ、心地よさを味わう中で、周囲の環境への関心を広げる。 - 準備するもの:
レジャーシートやベビーカー
日差しを避けられる場所(木陰など)、または日よけ
風で優しく揺れるもの(木の葉、モビールなどが見える場所) - 保育士の関わり方:
- 天候の良い日に、戸外の静かで安全な場所に子どもを寝かせたり、ベビーカーで座らせたりします。
- 「風が気持ちいいね」「お日さまがキラキラしてるね」など、保育士が感じたことを穏やかな口調で語りかけ、子どもの五感を刺激します。
- 子どもが空を見上げたり、木の葉の揺れを目で追ったり、じっと何かを見つめたりしている様子を、邪魔せずに優しく見守ります。
- 子どもの表情や手足の動きから、「心地よいのかな?」「何か気になっているのかな?」と気持ちを汲み取り、応答します。
【1歳児】「自分で!」が加速する!主体性を伸ばすアイデア
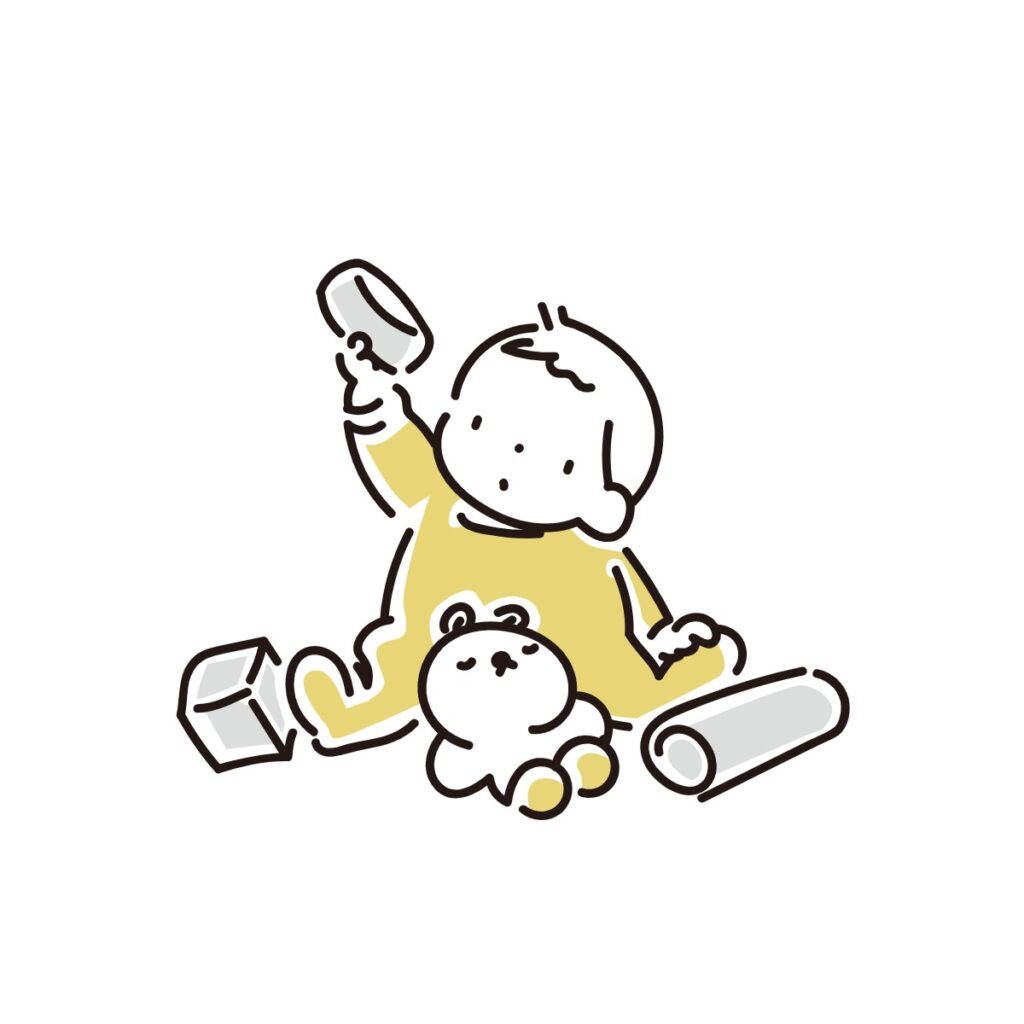
1歳になると、つかまり立ちや伝い歩きから、一人で歩けるようになる子が増え、行動範囲が一気に広がります。
指さしで自分の意思を伝えたり、簡単な単語を話したりするようにもなり、「自分でやりたい!」という自我がはっきりと芽生えてくる時期です。それはまさに主体性が育っている証拠。
保育士は、子どもの「やってみたい!」という気持ちを温かく受け止め、試行錯誤を見守りながら、できた喜びを共感し、自己肯定感を育むサポートを心がけましょう。
1歳児:室内遊びのアイデア指先と創造力を伸ばすかきかきぺったんアート
- ねらい
シール貼りやなぐり描きを通して指先の巧緻性を高め、自分の行為が形として現れる面白さを体験し、表現する喜びを知る。 - 準備するもの
大きめの画用紙など
様々な色や形、大きさのシール(子どもが自分で剥がしやすいもの)
持ちやすい太さのクレヨン、安全な水性ペン、フィンガーペイント用の絵の具
汚れても良いスモックやエプロン、床や机を保護するシート - 保育士の関わり方:
- まずは保育士が楽しそうにシールを貼ったり、クレヨンで伸び伸びと線を描いたりする様子を見せ、子どもの興味を引き出します。
- 子どもがやりたがったら、画用紙とシールやクレヨンを渡し、自由に表現させます。シールの台紙から剥がすのが難しい場合は、端を少しめくっておきましょう。
- 「ぺったんできたね」「ぐるぐる描けたね、面白い線だね」と、結果だけでなく行為そのものを認め、具体的に褒めます。
- 「ここに貼ってみようか?」と提案することはあっても、色や場所を指示したり、はみ出すことを注意したりせず、子どもの「自分で選んで、自分でやった」という感覚を大切にします。
- 完成した作品は、「〇〇ちゃんの作ったもの素敵だね!」と言って目立つ場所に飾り、達成感を共有します。
1歳児:戸外遊びのアイデア小さな発見がいっぱい「園庭たんけん隊」
- ねらい
自分の足で歩き回り、草花や虫、石、砂など、園庭にある様々な自然物に触れ、興味や好奇心を広げる。 - 準備するもの
小さなバケツやカップ、シャベルなど
帽子、動きやすい服装、汚れても良い靴 - 保育士の関わり方:
- 子どもたちが安全に自由に園庭を探索できるように、危険な場所や物は事前に確認し、取り除いておきます。
- 子どもが見つけたものに、「あ、アリさんだね。どこに行くのかな?」「きれいなお花見つけたね。いい匂いするかな?」と共感し、一緒に観察します。
- 子どもが何かをじっと見ていたり、拾い集めていたりする時は、その集中を邪魔せず、満足するまで見守ります。
- 「これは何だろう?」と子どもが指さしたものについて、「葉っぱだね。緑色で大きいね」などと、色や形、名前などを言葉で伝えます。
【2歳児】「自分で考えてやってみる!」が花開くアイデア
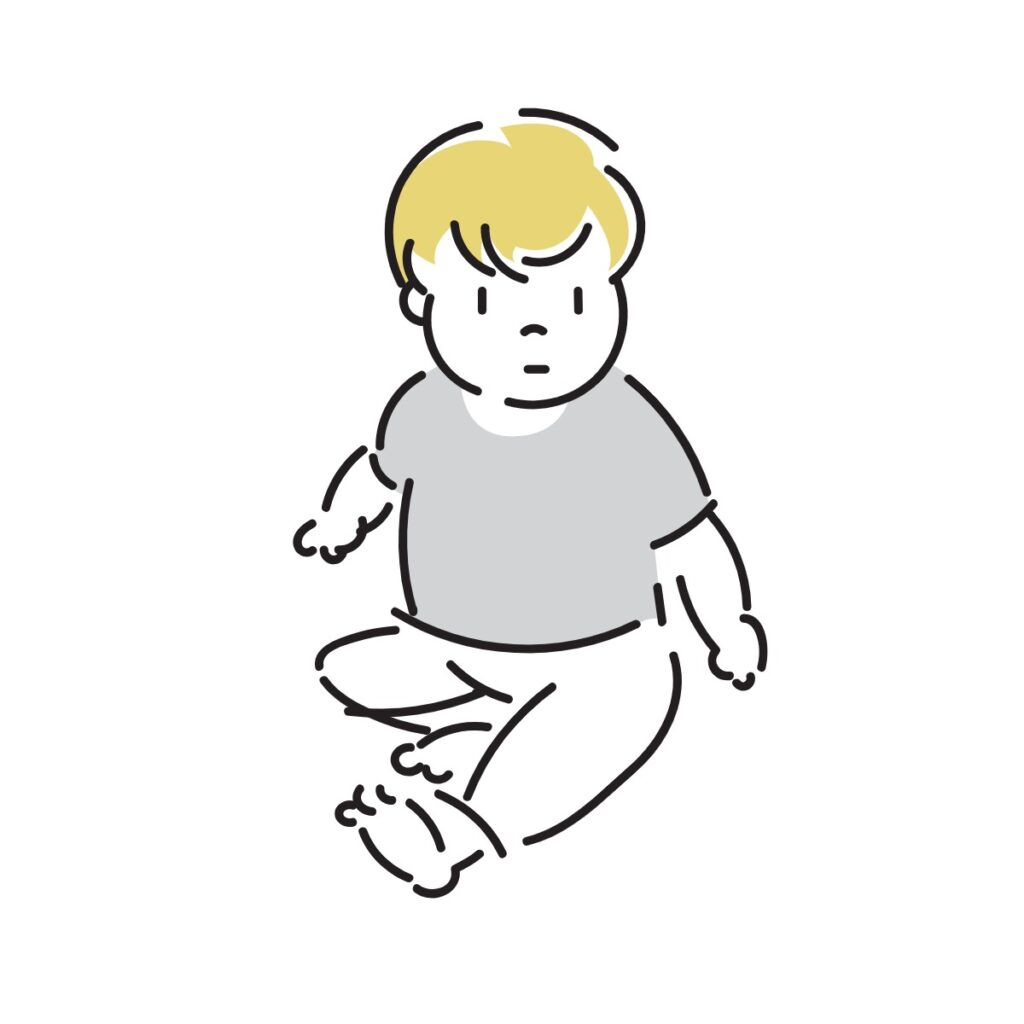
2歳になると、言葉でのコミュニケーション能力が飛躍的に伸び、二語文、三語文を話すようになります。
自我が一層強くなり、いわゆる「イヤイヤ期」もこの頃。しかしこれは、自分の意思を伝えたい、自分で決めたいという強い主体性の表れです。友達との関わりも増え、ごっこ遊びや簡単なルールのある遊びを好むようになります。
保育士は、子どもの「自分で考えたい」「こうしたい」という思いを受け止め、試行錯誤を励まし、自分なりの方法を見つけ出す喜びを支えることが大切です。葛藤やうまくいかない経験も、学びのチャンスと捉えましょう。
2歳児:室内遊びのアイデア想像力と社会性「みんなでごっこ遊びワールド」
- ねらい
自分のイメージや経験をもとに、役になりきったり、簡単なストーリーを作ったりして遊ぶ中で、想像力、社会性、言葉の力を育む。 - 準備するもの
お店屋さんごっこセット(レジ、お金、商品に見立てたもの、エプロン、看板など)など
段ボール、布、空き箱など、子どもたちが自由に見立てて使える素材 - 保育士の関わり方:
- 子どもたちの会話や興味関心から、どんなごっこ遊びがしたいかヒントを得て、コーナーを用意したり、子どもたちと一緒に作ったりします。
- 最初は保育士がお客さんになったり、一緒に役になりきったりして遊びを盛り上げますが、徐々に子どもたち自身で役割分担をしたり、ストーリーを展開したりできるように見守ります。
- 「いらっしゃいませ!何にしますか?」「次は僕が運転手!」「お熱測りますね」など、子どもたちの言葉のやり取りを促し、必要に応じて「〇〇ちゃんはこう言いたいのかな?」と仲立ちをします。
- 子どもたちが作ったルールやストーリーを尊重し、「ハンバーガーくださいって言ってたね。ポテトもつけるのかな?」と、子どもの世界観に共感しながら関わります。
2歳児:戸外遊びのアイデア:ルールを意識して楽しむ「追いかけっこ・集団ゲーム」
- ねらい
友達と一緒に体を思いきり動かす楽しさを味わいながら、簡単なルールを理解し、守ろうとする気持ちや社会性を育む。 - 準備するもの
安全で広いスペース(園庭、ホールなど)
必要に応じて、スタートラインやゴール、鬼の目印になるもの(コーン、帽子など) - 保育士の関わり方:
- 「まてまてー!」と保育士が鬼になって追いかけっこを始めるなど、まずは保育士が遊びの楽しさを伝えます。
- 「タッチされたら鬼を交代ね」「この線から出ないようにしようね」「赤信号の時はストップだよ」など、分かりやすい言葉でごく簡単なルールを伝えます。一度にたくさんのルールを伝えないのがコツです。
- 最初はルールを守れなかったり、自分の思い通りにいかなくて泣いてしまったりすることもあります。その際は、「悔しかったね。でも次はこうしてみようか」と気持ちを受け止め、優しく伝え、繰り返し経験する中で理解を促します。
- 友達とぶつかったり、順番を待てなかったりするトラブルも、社会性を学ぶ上で大切な経験です。保育士は、それぞれの気持ちを受け止めながら、どうすればみんなで楽しく遊べるかを一緒に考える機会を作ります。
- 「みんなで走ると楽しいね!」「〇〇ちゃん、捕まえるの上手だね!」「〇〇くん、速いね!」と、楽しさや頑張り、良い動きを具体的に言葉にして共有します。
まとめ:0・1・2歳児の主体性を育む保育の秘訣 – 子どもを信じ、待つ勇気
これまで、0歳・1歳・2歳児の主体性を育むための具体的なアイデアを、年齢別・活動別に見てきました。
最後に、低年齢児の主体性を育む保育において、特に大切にしてほしい秘訣をまとめます。
- 安心できる環境と応答的な関わり: 特定の保育士との愛着形成を基盤に、快・不快のサインに応答し、情緒の安定を図ります。これが外界への興味の第一歩です。
- 五感を刺激する豊かな経験: 様々な素材や自然に触れることで感覚を豊かにし、世界への好奇心を育てます。
- 「自分で動きたい」意欲の尊重: 寝返りやずりばいなど、自ら動こうとする意欲を支え、安全な環境で自由に探索させます。
- 「自分でやりたい!」気持ちの尊重: 自我の芽生えを温かく見守り、子どもの挑戦と達成感を大切にします。
- 表現する喜びの体験: シール貼りやなぐり描きなどの指先を使う遊びを通して、表現する楽しさや自己肯定感を育みます。
- 探索活動による好奇心の充足: 歩行の獲得と共に広がる行動範囲を活かし、園庭での探索活動や感触遊びで好奇心を満たします。
- 言葉による自己表現の促進: 自分の思いや考えを言葉で伝えようとする姿を受け止め、コミュニケーション能力を育てます。
- ごっこ遊び・集団遊びによる社会性の育成: 友達との関わりの中で、役割分担や簡単なルールを意識し、社会性の基礎を育みます。
- 試行錯誤の奨励と達成感の共有: 自分で考え工夫する過程を励まし、成功体験だけでなく努力も認めることで意欲を引き出します。
主体性保育は、よく「待つ保育」とも言われます。子どもが自分で気づき、考え、行動するまで、保育士は辛抱強く待つ姿勢が求められます。それは時に、手を出して教えた方が早いと感じることもあるかもしれません。しかし、その「待つ」時間こそが、子どもが自分自身の力で伸びていくための大切な時間なのです。
元園長として多くの0・1・2歳の子どもたちと関わってきましたが、一人ひとりの子どもが持つ力、伸びようとする力には本当に驚かされます。
保育士は、その力を信じ、子どもたちの「やってみたい!」という小さな芽を大切に育てる伴走者です。
この記事でご紹介したアイデアが、皆さんの保育現場で、子どもたちのキラキラした笑顔と「自分でできた!」という自信に満ちた表情を引き出すための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。